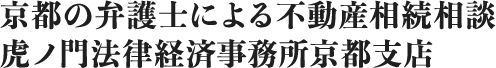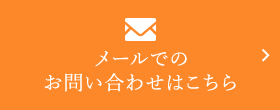1 はじめに
前回のコラムにおいて、遺産分割を進める上で、重要な3ステップがあることをお伝えしました。今回はその具体的な内容についてご紹介したいと思います。「相続人の範囲の確定」(ホップ)、「遺産の範囲の確定」(ステップ)、「遺産を分け方の確定」(ジャンプ)の順にご説明します。
2 相続人の範囲の確定(ホップ)
まず、「相続人の範囲の確定」、すなわち遺産を相続する人が誰かを確定する手続です。
相続人には、血族相続人と配偶者相続人の2種類が存在します。
血族相続人には順位(ランク)があり、先順位のランクの血族相続人がいないときにはじめて後順位のランクの血族相続人が相続人となります。具体的にいえば、第1順位ランクの相続人としては被相続人の子(もしくは代襲相続人となる直系卑属。民法887条)、第2順位のランクの相続人としては直系尊属(民法889条第1項1号)、第3順位の相続人は被相続人の兄弟姉妹となります(民法889条1項2号)。なお、「卑属」「尊属」という聞き慣れない言葉の意味ですが、卑属とは自分よりも下の世代(子や孫)、尊属とは自分よりも上の世代(親や祖父母)を指します。

一方、配偶者相続人は、被相続人に配偶者がいる場合に必ず相続人となります(民法890条)。血族相続人の順位に関わらず、常に相続人となるのが特徴です。 相続人の確定は、遺産分割協議を進める上で最初に行うべき、非常に重要な作業です。もし相続人が一人でも漏れてしまうと、その後に作成した遺産分割協議書が無効になる可能性もあります。戸籍謄本などを取り寄せ、慎重に確認することが求められます。
3 遺産の範囲の確定(ステップ)
相続人の範囲が確定できたら、次に「遺産の範囲の確定」に進みます。これは、被相続人が有していた遺産が何であるかを正確に把握する作業です。
遺産には、預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金といったマイナスの財産も含まれます。これらの遺産をすべて洗い出し、「遺産目録」を作成することが大切です。具体的な確認方法としては、まず預貯金については、被相続人が利用していた金融機関すべてに問い合わせ、死亡時の残高証明書を発行してもらいます。不動産は、固定資産税の納税通知書や登記簿謄本を確認することで把握できます。有価証券については、証券会社からの取引報告書や残高証明書を取り寄せる必要があります。その他、自動車、骨董品、貴金属など、評価が必要なものもあります。
見落としがちなのがマイナスの財産です。借入金がないか、連帯保証人になっていないかなども、しっかりと調査する必要があります(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターなどの信用情報機関に照会をかけることも有益です。ただし、個人からの借り入れは明らかにならないことに注意が必要です)。マイナスの財産がプラスの財産を上回るような場合には、相続放棄も検討する必要があります。
この「遺産の範囲の確定」は、遺産分割協議の土台となる部分です。財産の漏れや見落としがあると、後々のトラブルの原因になりかねません。必要に応じて、弁護士などの専門家の力を借りることも検討しましょう。
4 遺産の分け方の確定(ジャンプ)
相続人全員と遺産の全貌が明らかになったら、いよいよ「遺産の分け方の確定」へと進みます。これが、相続手続きの最終段階、「ジャンプ」です。
遺産の分け方は、原則として相続人全員の話し合い、すなわち遺産分割協議によって決定されます。法定相続分という目安はありますが、必ずしもその割合で分けなければならないわけではありません。特定の相続人が被相続人の介護に尽力していたり、事業の承継が必要であったりするなど、それぞれの事情を考慮して自由に分けることができます。
遺産分割協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書として書面に残します。この書面には、誰がどの財産を相続するのか、具体的に記載し、相続人全員が署名捺印(実印)します。遺産分割協議書は、不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなど、その後の手続きに必要不可欠な書類となります。
もし、遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停でも解決しない場合は、審判へと移行し、裁判官が判断を下すことになります。
5 おわりに
相続は、大切な家族を亡くした悲しみの中で進めなければならない、非常にデリケートな手続きです。今回ご紹介した「相続人の範囲の確定(ホップ)」、「遺産の範囲の確定(ステップ)」、「遺産を分け方の確定(ジャンプ)」という3つのステップを順に進めることで、スムーズな遺産分割を目指すことができます。
しかし、相続には専門的な知識や複雑な手続き(そして感情)が伴うことも少なくありません。ご自身だけで進めるのが難しいと感じたら、迷わず弁護士に相談することをおすすめします。
以上
(文責 弁護士 今井良輔)