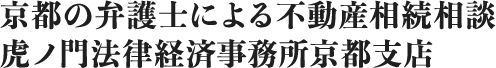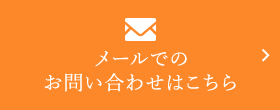1 「相続」と「遺産分割」の関係は?

よく「相続」と「遺産分割」を同じ意味の言葉のように使われることがあります。確かに、故人の方の遺産を引き継ぐという大きな意味では同じ事象を表した言葉なのですが、厳密にいえば両者は別の意味を持つ言葉です。
まず、「相続」は、故人(法律の世界では故人を「被相続人」と表現しますので以下「被相続人」といいます。)の法律上の地位を特定の者に承継させることをいい、その種類として法律による相続(法定相続)と遺言による相続(遺言相続)があります。
次に、「遺産分割」は、被相続人が死亡の時に有していた遺産について、誰がその遺産の権利者となるかを確定させる手続のことをいいます。すなわち、遺言によって全ての遺産の承継先が決まっていたり、相続人がそもそも一人しかいないような場合にが、「誰がその遺産の権利者となるかを確定させる手続」はそもそも不要ですので、遺産分割をする必要はありません。逆に言えば、遺言で承継先が決まっていない遺産が存在し、かつ、相続人が複数名いる場合には遺産分割が必要となります。
したがって、「遺産分割」は、「相続」という目的を達成するための手段(遺言相続以外の承継ですので、分類としては法定相続内の手段となります)であることが分かります。
2 遺産分割の機能について
(以下は遺言がない法定相続を前提として説明します)

前述したとおり、被相続人の相続人が一人の場合(例えば、父・母・子一人の家庭において、既に母が亡くなっており、今回父が遺言を残さずに亡くなったというケースでは、子一人のみが相続人となります)には、その一人だけが遺産を承継することは明らかですので、「誰が」その遺産の権利者となるかを確定させる必要はなく、遺産分割をする必要はありません(ただ、預金口座や不動産などの承継手続は必要となります)。
他方、相続人が複数いる場合(いわゆる共同相続)には、遺産が相続人の相続分にしたがって複数の相続人に共同で帰属(遺産共有・民法898条1項)していることになります。遺産共有状態においては、その使用関係、利用関係を民法249条以下の共有の規律に従うことになるので、権利関係の処理が非常に複雑となります(ある不動産を暫定的に複数名で所有しているので、その管理・利用の方法をいちいち他の相続人と話し合わなければならないのでその面倒さはイメージできるかと思います)。
そこで、相続人は、その遺産の終局的な権利者を誰とするのかを確定させる必要があり、その確定のための手段が「遺産分割」なのです。まさに遺産分割には遺産の終局的な帰属を確定させる機能があるということになります(民法909条)。
遺産分割を進める上で、実務上、重要な3ステップ(相続人の確定・遺産の確定・分割方法の確定)があるのですが、紙面の関係上、別の記事でご紹介します。
(文責 弁護士 今井良輔)