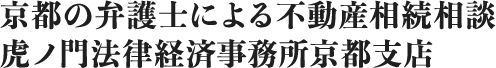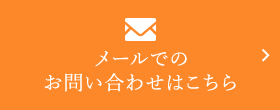1 遺産分割調停は、どこの家庭裁判所に申し立てるの?

前回、「相続の3ステップ!」でご説明しましたとおり、相続人の範囲の確定のためには戸籍謄本などを取り寄せて確認する必要がありますし、遺産の範囲の確定のために被相続人が利用していた金融機関から残高証明書を発行してもらう必要があるなど、遺産分割を進める上で、しなければならないことが結構あり、しかもこれがなかなか面倒なんですが、遺産分割調停を申し立てる際にも、これらのことを準備することは当然必要になります。
では、面倒な準備を終えてやっと遺産分割調停を申し立てることができる状態となったとして、どこの家庭裁判所に申し立てればいいのでしょうか。
それは、家事事件手続法に定められていまして、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者(相続人)が合意(管轄合意といわれるもので、遺産分割調停をどこの家庭裁判所で行うかについての合意のことをいいます。)して定めた家庭裁判所です。もっとも、管轄合意があることは稀であると思われますので、ほとんどの場合、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所ということになります。
そして、相手方(調停の場合、調停を申し立てた方を「申立人」、申し立てられた方を「相手方」といいます。)が複数人いる場合は、そのうちの誰か1人の住所地を管轄する家庭裁判所ということになります。
例えば、管轄合意がない場合において、相手方が、1人は滋賀県大津市に、もう1人が東京都千代田区に、それぞれ居住している場合は、大津家庭裁判所、又は、東京家庭裁判所のいずれかの家庭裁判所に、遺産分割調停を申し立てることになります。この場合、大津家庭裁判所に申し立てるか、東京家庭裁判所に申し立てるかは、申立人が、自由に決めて構いません。
2 では、具体的にどこの家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるべきかについて考えてみましょう。
例えば、被相続人が大阪市に居住していたところ、そこで死亡して相続が開始したところ、その相続人が、被相続人の長男、長女及び二女のきょうだい3人で(家庭裁判所では、「兄弟」、「兄妹」あるいは「姉妹」という漢字による表現ではなく、「きょうだ い」というひらがなで表現することがあるようです。)、長男は京都市に、長女は大津市に、二女は東京都千代田区に、それぞれ居住しており、長男と長女は遺産分割の内容についても意見が一致しているのに、二女のみがこれに反対して、遺産分割協議がまとまらない場合を考えてみます。
この場合、長男と長女は、意見が一致していることから、長男及び長女がともに申立人となって、遺産分割調停を申し立てることが考えられますが、そうすると、申立人は長男及び長女で、相手方は二女ということになりますから、二女が居住している住所地を管轄する東京家庭裁判所に申し立てる必要があります。でも、「反対しているのは二女だけなのに、なんで、遠い東京家庭裁判所に申し立てなあかんの?」と考える方もいらっしゃると思います(もっとも、遺産分割調停は、必ずしも家庭裁判所に出向く必要はなく、ウェブ会議の方法により参加(パソコンを利用して参加)することも認められていますので、あまり、遠方かどうかは考える必要はないのかも知れません。)。
このように考える方に対しては、「意見が一致しているからと言って、長男及び長女がともに申立人になる必要はなく、長男か長女のいずれかが申立人となり、残りのきょうだいを相手方として調停を申立てればいいでしょう。」というアドバイスが考えられます。
仮に長男のみが申立人となった場合、長女は相手方となりますから大津家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができますし、長女のみが申立人となった場合、長男は相手方となりますから、遺産分割調停は、京都家庭裁判所に申し立てることができます。二女からすれば、「何勝手なことをしているの!」ということになるのかも知れませんが、長男及び長女は、別に悪いことをしたわけではなく、法律をうまく利用したに過ぎません。
ただ、遺産分割調停は、話し合いで解決することを目指しますので、長男及び長女の意見に反対している二女の気持ちを考えることも必要です。仮に、長男あるいは長女のいずれかが申立人となって京都家庭裁判所、あるいは、大津家庭裁判所に、遺産分割調停を申し立てた場合、二女は、これまでの長男及び長女の意見に反対してきた態度を一層硬化させることが考えられます。また、長男及び長女が、ともに申立人となって遺産分割調停を申し立てた場合、二女が不快に感じるかも知れません。そうすると、遺産分割調停で合意に達することが難しくなることが予想されます。
きょうだいの関係は、当然のことながら千差万別であり、相手の気持ちを考えることは非常に難しいことですが、話し合いによる解決を目指すのであれば、「初めが肝心」ということを考えて、長男、あるいは、長女のいずれかが申立人となり、遺産分割調停を二女が居住する住所地を管轄する東京家庭裁判所に申し立てることも一つの方法であるように思います。
3 遺産分割調停を申し立てた家庭裁判所が、必ずしも、審判するとは限らないことについて

遺産分割調停を申し立てたとしても、当然のことですが、合意に達せず、調停が不成立となった場合、審判手続に移行します。ただ、合意に達しなかったとしても、必ずしも調停が直ちに不成立とならず、場合により、家庭裁判所が、「調停に代わる審判」をすることがありますが、「調停に代わる審判」については、また、別の機会にお話しします。そして、調停が不成立となって審判手続に移行した場合、遺産分割については、家庭裁判所が、「審判」という形式で結論を出すことになります。
ところで、遺産分割審判は、管轄合意がない限り、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所、すなわち、被相続人の最後の住所地(被相続人の死亡時の住所地)を管轄する家庭裁判所がすることになります。先ほどの例で説明すると、遺産分割審判は、被相続人が死亡した際の住所地を管轄する大阪家庭裁判所が行うことになりますので、遺産分割調停の申し立てを受けた家庭裁判所は、調停事件を、大阪家庭裁判所に移送することがあります。
ただ、調停をしていた家庭裁判所は、事情を把握しており、一定の心証を抱いていることも多く、比較的速やかに審判することができる状態にあることがありますが、このような場合、調停をしていた裁判所が、大阪家庭裁判所に移送することなく、審判することもあります(これを「自庁処理」といいます。)。
調停事件を、大阪家庭裁判所に移送するか、自庁処理するかは、調停をした家庭裁判所の判断になりますが、きょうだい(のだれか1人)が、自庁処理することについて反対している場合においては、調停をした家庭裁判所が、自庁処理することは少ないと思います。
(文責 弁護士 吉岡真一)